- 菅原道真公の命日はいつ?
- なぜ3月26日が命日と伝わらない?
- 菅原道真公は何歳まで生きた?
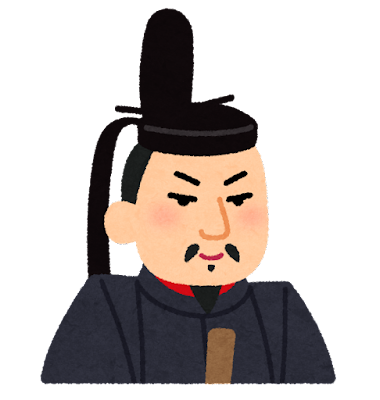 Mr.michizane
Mr.michizane
▶太宰府天満宮の参道にある企業 ▶「合格」に関する事業を展開 ▶何度もメディアに登場 ▶太宰府みやげの定番【学問のするめ®】100万袋以上販売
菅原道真公は、最終的に当時の日本で3番目に偉いとされる右大臣に出世しました。
家柄だけで考えると、とてもたどり着ける地位ではなかったはずですが、たった20名しかなれない文章生というエリートに18歳でなったり、そのエリートに学問を享受する立場である文章博士(もんじょうはかせ)にまでなりました。若干33歳のときです。
子煩悩であったり、信仰心が強かったりという面があって、徐々に出世し、宇多天皇からは非常に高い信任をおかれました。
そんな菅原道真公の命日はいつでしょうか?
菅原道真公は、延喜3年2月25日といわれていますが、正確には西暦903年3月26日です。
こんにちは。
(株)合格のヒロキタ・マイです。
神社仏閣が好きすぎて、太宰府天満宮の参道にある会社に就職した個性的すぎるアラフォー女子です。
そんな私が、菅原道真公の命日秘話について詳しく解説していきます。
菅原道真の命日は2月25日か3月26日か?

菅原道真公は、延喜3年2月25日に亡くなったとされています。
実際、多くの天満宮では、2月25日に何かしらの縁日行事があり、たくさんの参拝者が訪れています。
冒頭でお伝えしたように、菅原道真公の正確な命日は、西暦903年3月26日です。
では延喜3年2月25日とはなんでしょうか?
延喜3年2月25日は年号と旧暦で表した場合の菅原道真公の命日です。
延喜(えんぎ)は、醍醐天皇時代の年号で、西暦901年から西暦923年までの期間を指します。
また、旧暦とは古い暦(こよみ)の数え方で、例えば「天保暦」とか「時憲暦」などといくつかの種類はあるものの、月の満ち欠けに基づいて作られた太陰太陽暦の一種であることには変わりはありません。
ちなみに、現在はグレゴリオ暦という新暦を採用していますが、私たち日本人が普段使っているものなので、解説は割愛します。
暦(こよみ)については別記事「菅原道真の誕生日は6月25日ではない!?」で詳しく解説しているので、興味のある人はそちらを参照してください。
菅原道真の命日、なぜ2月25日説が広まっているのか?
私たちにはなじみのない旧暦で表された2月25日が菅原道真公の命日であると広まっています。
こちらも別記事「菅原道真の誕生日は6月25日ではない!?」で同様の内容を記載しているので、簡単にお伝えすると、誕生日も(6月)25日、命日も(2月)25日と、25日に縁があることが、非常に分かりやすいので、そのことを活かそうということになったんだと思います。
- 誕生日も(6月)25日
- 命日も(2月)25日
25日は菅原道真の日!
これを世間に広めようとしたのではないでしょうか?
同じように、「菅原道真といえば25日」、「25日といえば菅原道真」という印象がつけば、思い出す仕組みとしては、かなり優れていますよね!
記憶術の中には、覚える対象と数字を紐づけるやり方も珍しくありませんし、一度このことが世間に認知されれば定着するのはそれほど難しくはないでしょう。
日本には神道という宗教があります。
神道には「八百万神々(やおよろずのかみがみ)」という言葉があるように、800万人の神様がいます。
菅原道真公も800万人の大所帯の中のお一人であり、どうにか目立つ方法を考えないといけなかったんですね。
その方法として、誕生日と命日で重なる「25日」を活かした。
ということです。
これは、誰かが意図的に行ったことなのか、その時代時代の民衆の信仰の継続によるものなのかは分かりませんが、随分と浸透して、当たり前のように受け入れられています。
※(株)合格は、特定の宗教団体を支持しておりません。
菅原道真は何歳まで生きたのか?没年は西暦903年
西暦901年、当時でいえば、かなりの高齢である57歳で長く危険な旅を終えて太宰府に着き、京の都を想い続けながら、無念のうちに亡くなりました。
タイトルの繰り返しになりますが・・・
- 菅原道真は、享年何歳だったのですか?
- 59歳の時、西暦903年3月26日に亡くなりました。
そう、菅原道真公は京都から遠く離れた太宰府の地で59歳で亡くなりました。
菅原道真公の生きた平安時代の平均寿命は30歳~40歳であるという説があるので、59歳という年齢は決して早世ではありません。
むしろ長生きの仲間入りを十分に果たしていると言えるでしょう。
ただ、太宰府に移り住んでから、たった2年で死んでしまうというのは、ただならぬミステリーではありませんか!?
もしかしたら、太宰府への長旅が祟ってしまったという可能性があるとは思いませんか!?
菅原道真が京都から太宰府に向かった道程 -高齢なのに凄まじい移動距離!-

菅原道真公が太宰府に着いてたった2年でお亡くなりになった原因が、京都~太宰府の過酷な旅にあると仮定してみます。
菅原道真公が京都から太宰府に向かう旅がどれほどのものだったのかを少し想像してみましょう。
菅原道真公が仕えた宇多天皇~醍醐天皇時代、日本の中心は平安京にあり、京都御所や東寺は平安京のあった地域に当てはめた場合、すっぽりと収まってしまうそうです。
なので、スタート地点を京都御所、日本全国天満宮ナビでご紹介している天満宮の中で太宰府への旅程に立ち寄った伝説のあるものや伝承で通過したであろう天満宮を通過地点として、Googleマップで距離を測ってみました。
京都から太宰府まで、約730km・・・!
菅原道真公は享年59歳でした。
当時の平均寿命を30歳~40歳、間を取って35歳としましょう。
菅原道真公は、平均寿命の1.68倍生きていることになります。
ちなみに京都を発ったのは57歳の時。平均寿命の約1.62倍も生きた頃です。
現代の平均寿命を仮に80歳としたとき、80歳の1.62倍生きている人がいるとしたら、何歳でしょう?
80歳 × 1.62 ≒ 129歳!!!
つまり・・
菅原道真公は、129歳の人が730kmの旅をしたのと同様の距離を移動しました。
日本国の中枢にいた人です。
しかも、右大臣といえば朝廷のナンバー3という、偉い人の中の偉い人です。
現代日本でいえば、政府与党の幹事長のようなすごい人です。
それほど偉い菅原道真公が、親子ほどの年の差のある藤原時平の讒言(ざんげん=ありもしないうそをついて他人を陥れること)によって、そんな過酷な旅を強制されました。
無実の罪を着せられ、なんと太宰府への旅費は自分の貯金を出す命令をされたのです・・・!
さらに、到着後は給料もなく、部下もなく、政治に対する一切の口出しを禁止されました・・・!
体力を奪われ、権力を奪われ、お金も部下も取り上げられたら、誰だって寿命が縮まるのは当たり前だと思いませんか?
過酷な長旅や、ひどい待遇が菅原道真公の命を奪ったという確証はありませんが、なんともつらい最後です。
晩年に多少愚痴や小言吐いたことも、理解できる気がしますね・・・。
まとめ
菅原道真公は、延喜3年旧暦2月25日=西暦903年3月26日、59歳でその生涯を終えました。
後の世で神となり、天満大自在天神(てんまんだいじざいてんじん)・菅原道真と呼ばれるようになりました。
祟り神という汚名を受けるも、その生涯を知った人々は、子煩悩だった公のことや、讃岐で涙で見送られるような善政を行った公の人徳を知って、そのお人柄を持って神として慕われたのだと改めて感じたのではないでしょうか?
逆に、そうでなければ、死後1100年経ってもなお愛される「学問の神様・菅原道真」像は作られなかったことでしょう。
個人的な感想はここまでにして、事実だけを最後に記しておきます。
- 西暦845年8月1日に誕生。
- 西暦903年3月26日に死没。
- 享年59歳。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
(株)合格
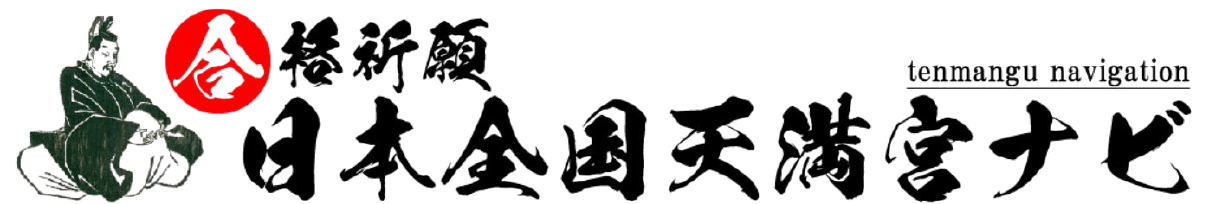




ありがとうございます。正確なお誕生日と没日がわかり、スッキリしました。それにしても藤原時平は許せない人物ですね〜(●`ε´●)
福田様
この度はコメントいただきまして、ありがとうございます。
日本人は古来より、数字的に法則が見つかるとそれに神秘性を持たせる。
天満宮では、信仰する神様のことをもっと知ってもらうためにそれを活かした、というところでしょうか。
素晴らしいのですが、本当の誕生日や命日が無視されてる感じは、毎年さびしい気持ちになります(*_*;
藤原時平は、人様を陥れたほんの数年のうち、因果応報という法則を経験したせっかちな方ですね(笑)
この度は、本当にありがとうございます。
[…] […]